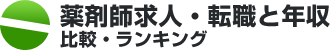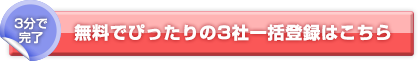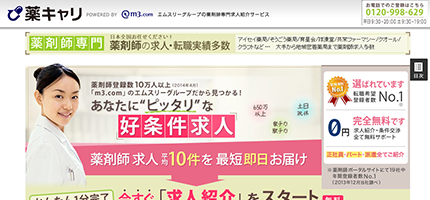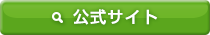「要指導医薬品」は、2013年に改訂薬事法により規定されました。言葉を聞いたことはあるかもしれませんが、実際にはどのような医薬品のことを指すのかが曖昧な人も多いでしょう。要指導医薬品は、薬剤師の仕事をするときに重要なキーワードになるので、言葉の定義をきちんと理解しておきましょう。
要指導医薬品とは?
要指導医薬品は、薬剤師による当該医薬品についての説明を受けなければ、基本的には購入できない医薬品を指します。一般的な市販薬と同様、薬局やドラッグストアなどで医師の処方箋なしでも購入できますが、必ず薬剤師による説明を受けなければいけません。当該医薬品の販売を行う薬剤師側は、購入者の情報を聞き出した上で、書面による説明を行います。そのため、薬剤師による説明が受けられないインターネットでは購入できない医薬品ですし、薬局・店舗側でも情報提供なしに購入できる場所には置かない決まりになっています。
要指導医薬品を販売するときのルール
要指導医薬品は、薬局の許可を受けているだけでは販売することができず、地域の保健所と厚生局に対して申請を行わなければなりません。薬事法に記載されている販売区分変更届などの文書を提出することで、初めて要指導医薬品を販売できるようになります。また、要指導医薬品を販売するときには、書類等を用いた薬剤師による対面での説明が必要になるため、インターネットで医薬品を販売している薬局・店舗では取り扱えないことになります。要指導医薬品だったものが一般医薬品に変更された場合は、インターネットで同様の医薬品を販売できるようになりますが、要指導医薬品の販売経験3年以上の薬剤師がサイトの管理者になる必要があります。
実際に要指導医薬品を販売したら、医薬品の品名・数量・販売日時・説明を行った薬剤師の氏名などを書類に記載し、最低でも2年間は保管します。購入者の連絡先も記載できれば良いですが、必ず聞き出さなければいけないわけではありません。